万国博覧会と日本の歩み ~過去・現在・未来をつなぐ懸け橋~
みなさんは「万国博覧会」と聞くと、どんなイメージを思い浮かべますか?
巨大なパビリオンが立ち並び、最先端のテクノロジーや多彩な文化が一度に体験できる国際的なお祭り……
実は、日本と万国博覧会の関わりは、意外にも幕末・明治期までさかのぼります。
日本が本格的に近代化へと舵を切った頃から、万博は「欧米技術を知るための窓口」や「日本文化を世界に発信する舞台」として大きな役割を担ってきました。
ここでは「万国博覧会と日本」の歩みを振り返りながら、これからの未来に向けた万博の可能性を一緒に考えてみましょう。
1. 万国博覧会とは何か
万国博覧会(Exposition Universelle / World’s Fair)は、世界各国が参加して産業・技術・文化などを披露し合う国際規模の博覧会です。
現在は、BIE(博覧会国際事務局)という機関が公認・管理を行っており、数年おきに世界各地で開催されています。
◆ 万国博覧会のはじまり
- 1851年:第一回ロンドン万国博覧会
産業革命の中心地だったイギリスが、自国の工業製品や技術を誇示するために開催。
会場の「クリスタル・パレス」は鉄とガラスでできた斬新な建築物として話題を呼びました。
こうした流れを受けて、ヨーロッパやアメリカ大陸など各地で万博が開かれ、各国が最新の工業製品や文化を紹介するイベントへと発展していきます。
◆ 万国博覧会の主な目的
- 国際交流・技術文化の共有
- 参加国の威信・技術力のPR
- 都市開発や建築技術の先行的実験
- 観光誘致・地域経済の活性化
19世紀~20世紀前半は「国威発揚」の色合いが強く、戦後は「平和と復興」、21世紀には「環境・持続可能性」が中心テーマになるなど、その時代の国際情勢が万博に反映されてきました。
2. 日本と万国博覧会の出会い
◆ 幕末~明治期:海外万博への初参加
日本が万国博覧会に初めて関わったのは、1867年のパリ万博とされています。
当時は開国して間もない時期で、幕府や薩摩藩などが出品した陶磁器や漆器が高い評価を受け、「ジャポニスム」の流行につながりました。
◆ 岩倉使節団と欧米視察
明治政府が積極的に万博へ参加したのは、岩倉使節団(1871~1873年)が欧米各国の最新技術・制度を視察したことが契機です。
万国博覧会を「欧米の先端技術を学び、自国文化を発信する場」と位置づけ、日本の近代化政策に活かそうとしました。
◆ 内国勧業博覧会の開催
明治期には国内でも「内国勧業博覧会」が開かれ、産業や技術の普及が進みました。
こうした博覧会文化の蓄積がのちに「自国で万博を主催する」動きへと繋がっていきます。
3. 万国博覧会の種類(BIEの区分)
国際博覧会を統括するBIEは、博覧会を大きく「登録博(Universal)」と「認定博(Specialized)」に分けて認定しています。
さらに別枠として「国際園芸博覧会(A1級)」なども存在します。
| 種類 | 登録博 (Universal) | 認定博 (Specialized) |
|---|---|---|
| 開催期間 | 最長6か月 | 最長3か月 |
| 会場面積 | 制限なし | 25ヘクタール以内 |
| テーマ | 広範かつ総合的 | 特定分野に焦点(例:海洋、科学技術、水など) |
| パビリオン | 国が独自に建設(大規模) | 共通展示館を区切る形(小規模) |
| 開催頻度 | 原則5年に1度(例外あり) | 登録博のない時期に開催可能 |
| 日本の例 | 1970年 大阪万博 2005年 愛知万博 2025年 大阪・関西万博(予定) |
1975年 沖縄海洋博 1985年 つくば科学万博 |
国際園芸博覧会(A1級)は、AIPH(国際園芸家協会)が主に認定する博覧会で、1990年に大阪で開催された「花の万博」がこれに該当します。
また、非BIE公認の大規模博(例:1964~65年のニューヨーク世界博)も存在します。
4. 日本で開催された万博の歩み
◆ 1970年 大阪万博

- 区分:登録博(Universal)
- テーマ:「人類の進歩と調和」
- 入場者数:約6422万人(当時世界最多)
戦後の高度経済成長真っ只中に開催され、家電、自動車、鉄鋼などの産業力を世界に示しました。
岡本太郎氏の《太陽の塔》がシンボルとなり、月の石の展示など未来的な要素も注目を集めました。
大阪都市圏の交通インフラ整備が進み、経済発展を後押しする大きな契機になっています。
◆ 1975年 沖縄国際海洋博(認定博)
「海―その望ましい未来」をテーマに、沖縄返還(1972年)後の地域振興を目的として開催。
会場跡地には沖縄美ら海水族館の前身施設が作られ、観光業の発展に貢献しました。
◆ 1985年 つくば科学万博(認定博)
「人間・居住・環境と科学技術」をテーマに開催。
ロボットや情報通信など最先端の技術を披露し、日本の“科学技術立国”イメージを強くアピール。
つくば市の研究学園都市としての発展を決定づけたイベントでもありました。
◆ 1990年 花の万博(国際園芸博)
AIPH(国際園芸家協会)認定の博覧会で、「人間と自然とのふれあい」をテーマに大阪で開催。
自然や環境保護の重要性を訴求した大規模イベントで、鶴見緑地の活用が進みました。
◆ 2005年 愛知万博(愛・地球博)

- 区分:登録博(Universal)
- テーマ:「自然の叡智」
- 入場者数:約2200万人
21世紀初頭の日本開催万博として、環境・持続可能性を強く打ち出した点が特色。
リサイクルや低公害車、磁気浮上式リニアモーターカー(リニモ)などを導入し、未来的な都市づくりを実験的に体現しました。
◆ 2025年 大阪・関西万博(予定)

- 区分:登録博(Universal)
- テーマ:「いのち輝く未来社会のデザイン」
- 会場:大阪湾の人工島「夢洲(ゆめしま)」
1970年以来、2度目となる大阪での世界博。
SDGsやポスト・コロナの課題を見据えた最先端技術の活用や、新しい国際交流の場として大きな期待が寄せられています。
開催後の夢洲開発をどう活かすかも大きな注目ポイントです。
5. 万国博覧会が日本にもたらすもの
◆ 技術吸収から技術発信へ
幕末・明治期は欧米の先端技術を吸収するために万博に参加していましたが、戦後~高度経済成長期にかけては日本が自国の技術や産業を世界に見せる立場へ転換。
1970年大阪万博で見せた家電や自動車産業の飛躍は、その後の日本経済を牽引する要因の一つとなりました。
◆ 地域振興・都市開発
万博開催時には会場建設や交通網の整備が進み、その後も「レガシー」として残るケースが多いです。
大阪万博(1970年)の跡地は万博記念公園に、愛知万博(2005年)の跡地は愛・地球博記念公園になり、現在も多くの人々に利用されています。
◆ 国際協力と平和のシンボル
戦後、日本は万博を通じて平和国家としての姿を国際社会に示し、各国のパビリオンが集うことで多様な文化交流が生まれました。
世界中が参加する博覧会は、単に国力を競うのではなく、人々が対話し協力する平和の祭典としての意義も持っています。
◆ 社会課題の解決とイノベーション
近年の万博は「環境・持続可能性・未来社会への対応」が大きなテーマ。
企業・大学・研究機関・NPO・市民団体などが共同で取り組むことで、新しいイノベーションを生み出す場としての役割が一層高まっています。
6. 今後に向けた展望と課題
◆ ポスト・コロナ時代の国際イベント
コロナ禍の影響で2020年のドバイ万博は2021~2022年に延期されました。
こうした状況を受け、オンライン参加やバーチャルパビリオンなど、デジタル技術を活用した新しい博覧会スタイルが模索されています。
◆ 巨大インフラ投資と「ポスト万博」
万博には多額の投資が必要なため、終了後に施設やインフラをどのように活かすかが重要です。
大阪・関西万博(2025年)でも、夢洲再開発や統合型リゾート(IR)構想など「ポスト万博」の使い道が議論されています。
◆ 多様性と共創のプラットフォーム
従来の「国の威信を競う場」から、国際課題を協力して解決する「共創の場」へ――万博は大きく役割を変えつつあります。
日本は技術力やホスピタリティのみならず、丁寧な合意形成や安全管理の分野でもリーダーシップを発揮できる可能性があります。
7. まとめ:万博がつなぐ「過去・現在・未来」
いかがでしたか?
万国博覧会は、日本の近代化や戦後復興、高度経済成長、さらに21世紀の環境問題にいたるまで、時代の節目を映し出す“鏡”ともいえる存在でした。
幕末・明治期には「欧米の先端技術を学ぶ場」、戦後~高度成長期には「日本の技術と経済力を世界に示す舞台」、そして現代では「地球規模の課題を解決するための共創プラットフォーム」へと変化してきています。
2025年には、再び大阪の地で大規模な世界博が開催予定です。
私たち一人ひとりが「万博」の歴史を知り、未来を担うイベントとしてどう活用できるのかを考えることは、きっとこれからの社会づくりにも役立つはず。
ぜひ、次の万博を通じてどんな未来が描かれるのか、みなさんも一緒に想像を巡らせてみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
また次回の記事でお会いしましょう!
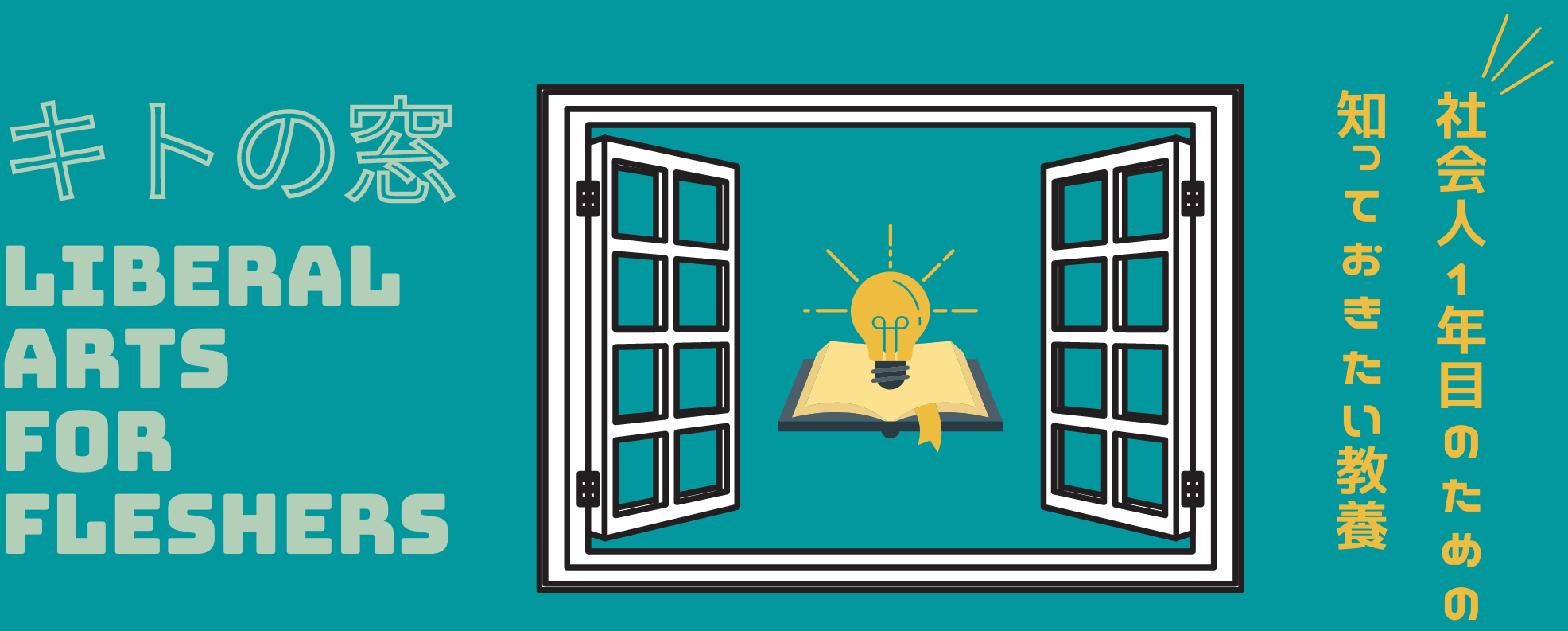


コメント